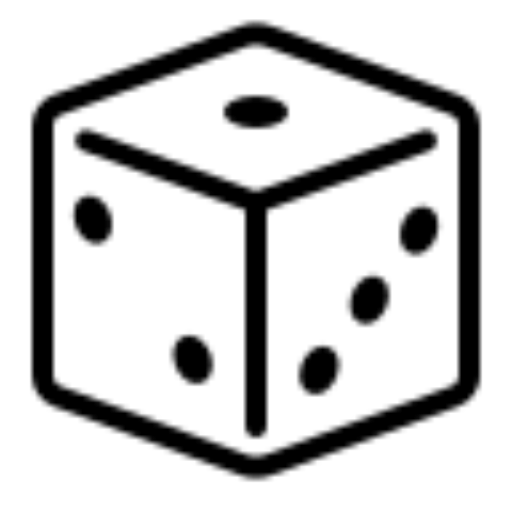今回は、私が最も愛する日本文学の一つ、梶井基次郎の『檸檬』を紐解いていきます。
本記事では、以下の3つのポイントを中心にストーリーを追っていきます。
① 主人公の精神状態を紐解く
② 檸檬を魅せる圧倒的描写力
③ なぜ丸善を「檸檬」で破壊した?
【動画版はこちら】
主人公の精神状態を紐解く
では、ストーリーを最初から順に読んでいきましょう。
物語冒頭では、主人公の置かれている状況や精神状態が描写されます。
えたいの知れない不吉な塊が私の心を始終圧えつけていた。
焦躁と言おうか、嫌悪と言おうか――
酒を飲んだあとに宿酔があるように、酒を毎日飲んでいると宿酔に相当した時期がやって来る。
それが来たのだ。これはちょっといけなかった。引用:『檸檬』(梶井基次郎)
まずは主人公が自身の精神状態を語り始めます。彼は「不吉な塊」に、心を押さえつけられているそうです。
それは焦燥や嫌悪に似た感情であるが、その正体はハッキリしない。「えたいの知れない」モノだと言います。
何かストレスや嫌な出来事があってモヤモヤしているのかと思いきや、どうやら少し違うようです。
結果した肺尖カタルや神経衰弱がいけないのではない。
また背を焼くような借金などがいけないのではない。いけないのはその不吉な塊だ。引用:『檸檬』(梶井基次郎)
主人公は病気を患っていたり、神経を弱らせていたり、大きな借金を抱えていたりと、「憂鬱になるような要素・出来事」には確かに心当たりがあります。
しかし「不吉な塊」を生み出している正体は、それらの出来事と直接結びついているわけではありません。彼が抱えているのは「ただ漠然とした不安」なのです。
『檸檬』という作品をより楽しむには、この「不吉な塊」に共感できるかが鍵となります。
何となく鬱々とした気分が、自分の心を侵食している。それは「将来への不安」かもしれないし「死への恐怖」かもしれない。「怠惰による焦燥」や「自分という存在のゆらぎ」かもしれません。
きっと色々なモノが複合的に混じり合って、具体的な対処や解決が不可能な「漠然とした不安」として存在しているのでしょう。
これは、芥川龍之介が『或旧友へ送る手記』で遺した言葉にも通じるものがあります。
君は新聞の三面記事などに生活難とか、病苦とか、或は又精神的苦痛とか、いろいろの自殺の動機を発見するであろう。
しかし僕の経験によれば、それは動機の全部ではない。のみならず大抵は動機に至る道程を示してゐるだけである。
が、少なくとも僕の場合は唯ぼんやりした不安である。何か僕の将来に対する唯ぼんやりした不安である。引用:『檸檬』(梶井基次郎)
有名な「唯ぼんやりした不安」という表現。芥川もまた、嫌な出来事が直接的に死の動機に結びつくわけではないという見解を示しています。
私は『檸檬』を読んだ当時から「不吉な塊」には激しく共感しています。特に「押さえつけていた」という表現が秀逸です。この感覚は、本当に心臓を鎖でゆるやかに締め付けられているような「圧迫感」に近い。実際に感じているからこそできる、繊細な表現だと思います。
主人公はその不吉な塊に心を支配されています。それによって何が引き起こされるのでしょうか。
以前私を喜ばせたどんな美しい音楽も、どんな美しい詩の一節も辛抱がならなくなった。
蓄音器を聴かせてもらいにわざわざ出かけて行っても、最初の二三小節で不意に立ち上がってしまいたくなる。
何かが私を居堪らずさせるのだ。それで始終私は街から街を浮浪し続けていた。引用:『檸檬』(梶井基次郎)
昔は好きだったモノが、純粋に楽しめなくなってしまったのです。本作品はこの「現在」と「過去」の時間軸による対比描写が肝になります。
(正確にはこの「現在」も過去を回想して書かれているのですが、今は「現在」「過去」の2軸で考えて大丈夫です)
主人公はかつて、美しい音楽や詩を純粋に楽しめていたのに、今となってはどうにも落ち着かない状態になってしまった。これはもちろん「不吉な塊」が原因です。モヤモヤを抱えたまま趣味に没頭するのは難しいものです。
歌や詩を楽しめなくなった彼は、どのようなモノを好むようになったのでしょうか。
何故だかその頃私は見すぼらしくて美しいものに強くひきつけられたのを覚えている。
風景にしても壊れかかった街だとか、その街にしてもよそよそしい表通りよりもどこか親しみのある、
汚い洗濯物が干してあったりがらくたが転がしてあったりむさくるしい部屋が覗いていたりする裏通りが好きであった。引用:『檸檬』(梶井基次郎)
「見すぼらしくて美しいもの」
作品の中では「壊れかかった街並」「生活感のある裏通り」などが挙げられています。先ほどの音楽や詩もそうですが、「分かりやすい美しさ」を内包するキラキラとした魅力が受け付けなくなったのです。
かといって美しいもの自体が嫌いなわけではなく、根底に美的センスは備えている。だからメインストリームから少し離れた「地味さ」「仄暗さ」「見すぼらしさ」の中にある美しさが好きになったのだと私は解釈します。メインカルチャーを忌避する感情に近いものがあるかもしれません。
続いて、そんな主人公が始めたとある空想の場面です。
時どき私はそんな路を歩きながら、ふと、そこが京都ではなくて京都から何百里も離れた仙台とか長崎とか――
そのような市へ今自分が来ているのだ――という錯覚を起こそうと努める。
我は、できることなら京都から逃げ出して誰一人知らないような市へ行ってしまいたかった。
主人公にとって京都とは、自分の忌まわしさと密接に紐づく場所。自分が暮らしている家や街には、現在の「鬱々とした自分」を形作ってきた「過去」が存在します。それは風景であったり、場所であったり、人間関係であったり。
だからもう全部忘れて「どこか遠い土地へ行きたい」と願う。もし彼が仙台で暮らしていたら、京都に来たいはずなのです。大事なのは自分の過去や思い出が介在しないこと。
続いて、どこか遠くへ行った自分の姿を空想する場面です。
第一に安静。がらんとした旅館の一室。清浄な蒲団。
匂いのいい蚊帳と糊のよくきいた浴衣。そこで一月ほど何も思わず横になりたい。
希わくはここがいつの間にかその市になっているのだったら。引用:『檸檬』(梶井基次郎)
「清浄な布団」という表現が素晴らしい。旅館やホテルが醸し出す特別感は、この「清潔さ」が大きな部分を占めると思います。「糊のよく効いた浴衣」のパリッとした感じ、備品が新品のように綺麗な状態であること。
過去も人間関係も一旦忘れて、静かで人気の無い部屋で、清潔で匂いの良い空間に包まれながら横になる……これほど素晴らしいことはありません。
さて、ここからは主人公が「今でも好きなもの」や「今だからこそ好きになったもの」について描かれます。
私はまたあの花火というやつが好きになった。
花火そのものは第二段として、あの安っぽい絵具で赤や紫や黄や青や、さまざまの縞模様を持った花火の束、中山寺の星下り、花合戦、枯れすすき。
それから鼠花火というのは一つずつ輪になっていて箱に詰めてある。そんなものが変に私の心を唆った。引用:『檸檬』(梶井基次郎)
(※花火そのものは第二段として……発火の美しさは二の次として、おもちゃの花火そのものの姿が好きになった、という意)
主人公は花火の「姿形」を気に入ったようです。地味だったり、色合いがチープだったりする体裁をむしろ気に入っている。ここでも「地味さ・単純さの中にある美しさ」に惹かれていることが分かります。
また、花火の他には「南京玉」「びいどろ(おはじき)」も好きになっています。
あの、びいどろの味ほど幽かな涼しい味があるものか。
引用:『檸檬』(梶井基次郎)
彼は、おはじきを口に含んで味わっています。ガラス細工特有の仄かな清涼感、無機質な冷たさを楽しんでいるのでしょう。「幽かな」と表現されている通り、やはりここでも「控えめさ」「地味さ」を好んでいます。
ここでのポイントは「清涼感」です。彼がこれらを好む理由は、単に「みすぼらしくて美しい」だけでなく、「爽やかさ」によって鬱屈とした感情や重い空気を和らげてくれるからだと思います。これは後々の「檸檬」の描写にも繋がる重要な要素です。
生活がまだ蝕まれていなかった以前私の好きであった所は、たとえば丸善であった。
赤や黄のオードコロンやオードキニン。洒落た切子細工や典雅なロココ趣味の浮模様を持った琥珀色や翡翠色の香水壜。煙管、小刀、石鹸、煙草。
私はそんなものを見るのに小一時間も費すことがあった。そして結局一等いい鉛筆を一本買うくらいの贅沢をするのだった。
しかしここももうその頃の私にとっては重くるしい場所に過ぎなかった。書籍、学生、勘定台、これらはみな借金取りの亡霊のように私には見えるのだった。引用:『檸檬』(梶井基次郎)
『檸檬』において「丸善」は非常に重要な場所です。少し深掘りしましょう。
現在も各地で営業されている大手書店ですが、梶井基次郎の時代(明治~大正)においては、もう少し異なる意味合いを持っていました。
明治時代、西洋の文化が積極的に輸入される文明開化が起こりました。丸善は明治2(1869)年に創業され、その西洋文化を積極的に取り入れるお店でした。新しい知識や文化を得ようとする人々の期待に応える場所として、洋書を中心とした書籍や、万年筆、タイプライター、香水、ランプなどの西洋的でオシャレな雑貨が置かれていました。
当時の「文明最先端」であり、「知的好奇心を刺激する場所」「生活を豊かにする文明的な場所」の象徴が丸善だったのです。

かつてはこの場所が好きだった主人公ですが、今や丸善は重苦しい場所になってしまいました。これには、序盤に書かれた「肺尖カタル」と「背を焼く借金」がヒントになります。
「肺尖カタル」は肺結核の初期症状と診断されることが多い病気で、実際に梶井は31歳という若さで結核で亡くなっています。主人公にとって「死」という存在はとても身近なものでした。病気による不健康な状態や、死を身近に感じることから来る憂鬱・不安・恐怖は、間接的に「不吉な塊」を形づくっていたはずです。
そして「背を焼くほどの借金」
彼は身体的な不健康さと、精神的な不健康さを併せ持っていました。これにより、「心身ともに健康あればこそ」楽しめる文化的・芸術的なものが楽しめなくなっているのだと私は解釈します。
「知的」「文化的」「芸術的」、そして「西洋的」なものを心から楽しむには精神的な余裕が必要です。その象徴である丸善は、今の彼にとって忌まわしい場所になってしまったのです。
ここで、彼の「苦手なもの」と「好きなもの」を整理してみましょう。
- 苦手なもの(かつて好きだったもの)
- 「知的なもの」
- 「西洋的なもの」
- 「芸術的なもの」
- 「派手なもの・豪華なもの」
- 好きなもの(現在惹かれているもの)
- 「落ち着いているもの」
- 「清涼感・爽やかさのあるもの」
- 「地味さ・みすぼらしさの中にある美しいもの」
押さえておきたいのは、苦手なものも「昔は好きだった」ということ。まるっきり魅力を理解できなくなったわけではなく、精神状況によって楽しめなくなっているだけなのです。
実際、梶井自身は西洋的な文化を大変好んでいました。お洒落な西洋雑貨を揃え、洋食やリプトンの紅茶を愛していました。しかし、「不吉な塊」のせいでそれを楽しめなくなった。「現在・過去」の時間的な対比軸として捉えることが重要です。
さて、この後主人公は街を転々と歩き続けた先で、かねてから気に入っていた果物屋さんに立ち寄ります。
檸檬を魅せる圧倒的描写力
ここからは果物屋さんで買った檸檬の描写と、それを手に入れた主人公の心情描写が中心となります。
その日私はいつになくその店で買物をした。というのはその店には珍しい檸檬が出ていたのだ。
いったい私はあの檸檬が好きだ。レモンエロウの絵具をチューブから搾り出して固めたようなあの単純な色も、それからあの丈の詰まった紡錘形の恰好も。引用:『檸檬』(梶井基次郎)
ここで使われている「いったい」は、「かねてから」と「本当に」が合わさったような美しい言葉遣い。
結局私はそれを一つだけ買うことにした。それからの私はどこへどう歩いたのだろう。私は長い間街を歩いていた。
始終私の心を圧えつけていた不吉な塊がそれを握った瞬間からいくらか弛んで来たとみえて、私は街の上で非常に幸福であった。
あんなに執拗った憂鬱が、そんなものの一顆で紛らされる――あるいは不審なことが、逆説的なほんとうであった。引用:『檸檬』(梶井基次郎)
最後の一文、「あるいは不審なことが、逆説的なほんとうであった。」という言葉。
「逆説的」とは、「急がば回れ」のように一見矛盾する言葉によって一つの真理を示すこと。
自分を苦しめていた「人生における大きな問題」が、檸檬という「たった一つの小さな果物」によって解消された。
これはあまりに不思議なことだが、自分の感情が証明してしまった以上、それは真理である。というニュアンスになります。
その檸檬の冷たさはたとえようもなくよかった。その頃私は肺尖を悪くしていていつも身体に熱が出た。(中略)
その熱い故だったのだろう、握っている掌から身内に浸み透ってゆくようなその冷たさは快いものだった。
私は何度も何度もその果実を鼻に持っていっては嗅いでみた。それの産地だというカリフォルニヤが想像に上って来る。
漢文で習った「売柑者之言」の中に書いてあった「鼻を撲つ」という言葉が断れぎれに浮かんで来る。
そしてふかぶかと胸一杯に匂やかな空気を吸い込めば、ついぞ胸一杯に呼吸したことのなかった私の身体や顔には温い血のほとぼりが昇って来てなんだか身内に元気が目覚めて来たのだった。引用:『檸檬』(梶井基次郎)
『檸檬』の魅力はこの圧倒的描写力。
主人公が檸檬を手にしてからの表現を振り返ると、「視覚」「触覚」「嗅覚」の順に五感を駆使して描写されていることが分かります。
嗅覚から記憶を呼び起こす手法もさることながら、「鼻を撲つ」という表現が秀逸。柑橘系の香りが鼻の奥をトンッと突く感覚を想起させます。そして全身に巡る感覚を描写することで、読者自身が檸檬の質感を全身で感じられるようにしている。
また、文学的な構造にも触れておきましょう。
この作品における「過去」と「現在」の対比の中で、檸檬はどちらの位置づけでしょうか。
檸檬が日本に広まったのは明治初期。かつて梶井が好んでいた西洋文化の一つです。「カリフォルニアが想像に上ってくる」という記述も西洋を想起させます。
一方で「檸檬」と漢字表記にし、漢文という要素と結びつけてもいる。さらに「檸檬などごくありふれている」とも書かれています。
つまり、檸檬は「現在と過去の垣根を超えた、真の美しさ」の象徴なのです。その根拠は、次の文章から読み取れます。
――つまりはこの重さなんだな。――
その重さこそ常づね尋ねあぐんでいたもので、疑いもなくこの重さはすべての善いものすべての美しいものを重量に換算して来た重さであるとか、
思いあがった諧謔心からそんな馬鹿げたことを考えてみたり――なにがさて私は幸福だったのだ。引用:『檸檬』(梶井基次郎)
この「重さ」こそが、自分がずっと探していたもの。
「知的・文化的・西洋的」という枠組みや、「みすぼらしさ・地味さ」という枠組みすら超えた、「自分にとって真に美しいもの」という価値観。自分の幸せを凝縮させた、「私自身」が見出した幸福なのです。
そして、その真の美しさを「檸檬の重み」で表現している点が秀逸。檸檬は手のひらサイズの軽い果実です。
私が求めていた救いや美しさは、偉大なものでも、特別なものでもなかった。結局、人間が求めている美しさや幸せは、このくらいの質量なんだろう。「つまりはこの重さなんだな」と。
「思い上がった諧謔心(かいぎゃくしん)」というのは自虐でしょう。自分の中では確信しているけれど、傍から見たら馬鹿げていることも分かっている。言葉遊びに過ぎないかもしれないが、「自分が今幸福だ」という事実は確かにここにある。それが檸檬のおかげなのは間違いない、というニュアンスです。
なぜ丸善を「檸檬」で破壊した?
いよいよ終盤です。気持ちが軽くなった主人公は、憂鬱な場所である丸善に立ち寄ろうと決意します。
しかしどうしたことだろう、私の心を充たしていた幸福な感情はだんだん逃げていった。
香水の壜にも煙管にも私の心はのしかかってはゆかなかった。引用:『檸檬』(梶井基次郎)
檸檬の力を持ってしても、丸善の憂鬱には勝てませんでした。
彼はとりあえず画本を棚から出してパラパラとめくりますが、どうにもならない。取り出した本がうず高く積まれていく中、不意にアイデアが閃きます。
「あ、そうだそうだ」その時私は袂の中の檸檬を憶い出した。
本の色彩をゴチャゴチャに積みあげて、一度この檸檬で試してみたら。
「そうだ」
私にまた先ほどの軽やかな昂奮が帰って来た。(中略)
やっとそれはでき上がった。そして軽く跳りあがる心を制しながら、その城壁の頂きに恐る恐る檸檬を据えつけた。そしてそれは上出来だった。
見わたすと、その檸檬の色彩はガチャガチャした色の階調をひっそりと紡錘形の身体の中へ吸収してしまって、カーンと冴えかえっていた。引用:『檸檬』(梶井基次郎)
「絵具をチューブから搾り出したような単純な色」が、重厚な画本たちの複雑な色合いの中で際立ち、周囲の雰囲気を緊張させる。以前語られた檸檬の特徴が、ここで見事に生きてきます。
不意に第二のアイディアが起こった。その奇妙なたくらみはむしろ私をぎょっとさせた。
――それをそのままにしておいて私は、なに喰わぬ顔をして外へ出る。――
丸善の棚へ黄金色に輝く恐ろしい爆弾を仕掛けて来た奇怪な悪漢が私で、もう十分後にはあの丸善が美術の棚を中心として大爆発をするのだったらどんなにおもしろいだろう。
「そうしたらあの気詰まりな丸善も粉葉みじんだろう」
そして私は活動写真の看板画が奇体な趣きで街をいろどっている京極を下って行った。引用:『檸檬』(梶井基次郎)
物語はここで終わります。最も印象的な「檸檬が爆弾になる」シーンです。
「丸善」が「主人公が過去に好きだった価値観の象徴」であり、「檸檬」が「主人公自身が見出した美しさや幸せ」であるならば、これは過去の価値観への決別を意味しているのではないでしょうか。
当時、西洋的な美は知識人や文化人にとって「イケているもの」でした。そういった現実に蔓延る価値観を、主人公の「想像」によって破壊したかった。作品を通じて、主人公は「想像」を用いて現実の「不吉な塊」に対抗しようとしており、「現実への抗い」が大きなテーマとなっているように感じます。
彼にとって忌々しい場所である丸善を破壊したい。それを自分が見出した「檸檬」によって行う。この意図については様々な解釈が可能で、非常に面白いポイントです。
純文学の紐解き方
文学的な構造を探るのも面白いのですが、私が『檸檬』に惹かれているのは、その美しい言葉遣い、繊細な心理描写、そして心から共感できる主人公の感性です。
純文学を楽しむには「共感性」や「シンクロ性」が重要だと考えています。純文学は、物語の起承転結が劇的に面白いわけではありません。
だからこそ、登場人物の心情や筆者独特の表現に自分が惹かれるかどうかが鍵。人によって合う・合わないが激しいジャンルですが、だからこそ「運命的な出会い」をした文学は一生の宝物になります。
皆様が、ご自身にとっての檸檬に出会えることを祈っております。
 憧れていた『檸檬』の聖地を歩く|京都市中京区
憧れていた『檸檬』の聖地を歩く|京都市中京区
檸檬(新潮文庫) | 梶井基次郎|本 | 通販 | Amazon